インタビュー
公共と自由のあり方を考える
PUMPQUAKES









曲線にて販売中。 https://kyoku-sen.com/items/5f69a0fe07e163296911e40f
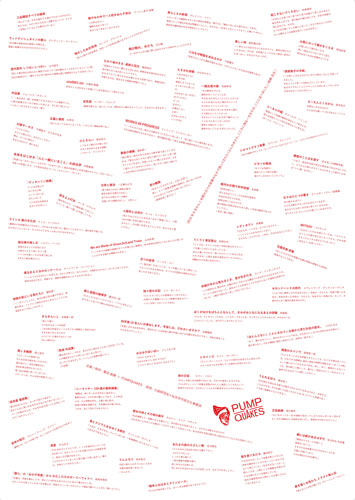
掲載:2021年7月9日
取材:2021年1月
企画・取材・構成 奥口文結(FOLKGLOCALWORKS)、濱田直樹(株式会社KUNK)
このインタビューは、「多様なメディアを活用した文化芸術創造支援事業」の助成事業実施者に文化芸術活動や新型コロナウイルス感染症の影響等について伺ったものです。
当日は、身体的距離確保やマスク着用などの新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、取材を行いました。写真撮影時には、マスクを外して撮影している場合があります。
- PUMPQUAKES パンプクエイクス
-
志賀理江子(写真家)、清水チナツ(インディペンデント・キュレーター)、長崎由幹(ロックカフェピーターパン後継、タコス愛好家、映像技術者)、佐藤貴宏(音響/ヴィジュアル/映像作家)、菊池聡太朗(建築家、美術家)からなる、宮城県を拠点としたインディペンデントな個人の集まり。作品制作、編集、キュレーションなど、ときどきに協働しながら、学びと表現をおこなっている。
団体名「PUMPQUAKES(パンプクエイクス)」は「PUMP(心臓・循環器・鼓動)」と「QUAKES(揺れ)」をあわせた造語。2011年3月11日の大地震をきっかけに出会ったメンバーからなるコレクティブで、個々の活動を持ち寄り学び合い、それらを循環させ、新たな揺れに変換していく試みを続けている。





